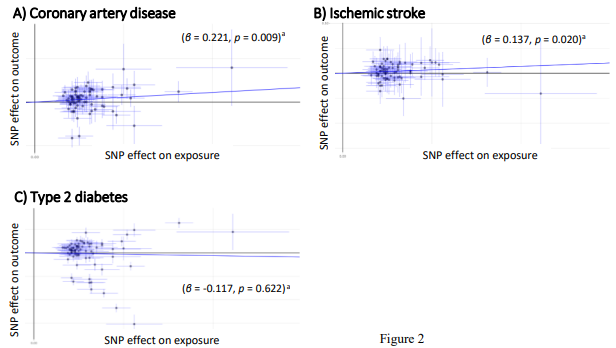自称・統計家
@biostat0718
駆け出しの生物統計家 / 看護師・保健師 /
臨床研究 / 治験 / MPH(Master of Public Health) / 公衆衛生大学院 / SAS, Rユーザー / 備忘録として日々の学びや気付きをつぶやく
ID: 1453257641082462212
27-10-2021 07:10:18
143 Tweet
238 Takipçi
225 Takip Edilen






#J_Epidemi Most viewed on J-Stage (Feb. 2023): BMI and cardiometabolic traits in Japanese: a Mendelian randomization study Mako Nagayoshi et al. doi.org/10.2188/jea.JE… Journal of Epidemiology