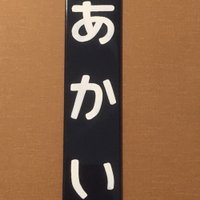日本史史料研究会
@nihonshishiryo1
史料にもとづいた日本史の研究会です。生駒 哲郎が自由に書き込んでます。
ID: 955013771415597056
http://www13.plala.or.jp/t-ikoma/ 21-01-2018 09:46:41
9,9K Tweet
6,6K Followers
5,5K Following





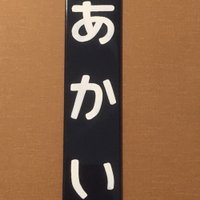










@nihonshishiryo1
史料にもとづいた日本史の研究会です。生駒 哲郎が自由に書き込んでます。
ID: 955013771415597056
http://www13.plala.or.jp/t-ikoma/ 21-01-2018 09:46:41
9,9K Tweet
6,6K Followers
5,5K Following