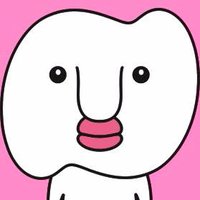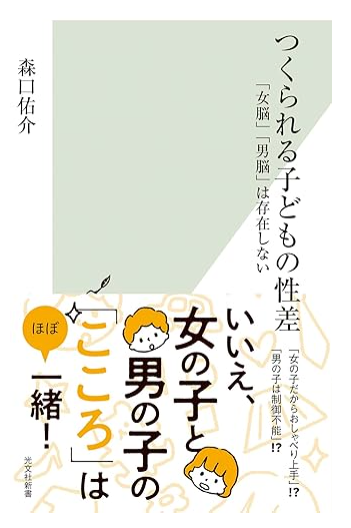森口佑介『つくられる子どもの性差: 「女脳」「男脳」は存在しない』(光文社新書 )
@moriguchiy
A Developmental Psychologist /発達心理学者です。
主著『10代の脳とうまくつきあう』(ちくまプリマー新書)『子どもから大人が生まれるとき』(日本評論社)
『子どもの発達格差』(PHP新書)
『自分をコントロールする力』(講談社現代新書)
『おさなごころを科学する』(新曜社)
ID: 280330544
https://sites.google.com/view/moriguchidevscilab/home 11-04-2011 03:45:41
4,4K Tweet
4,4K Followers
30 Following



今、自分がアラヤやムーンショットなどの様々な活動を通して何を目指しているのか、根本的なモチベーションについて書いてみた。そして、それが実現できていないもどかしさについても。 僕が様々な活動をしている理由|Ryota Kanai Ryota Kanai 🌙 #note note.com/kanair/n/ne050…









”SNSで「さす九」というスラングが話題になりましたが、私も結婚したら女性が姓を変えるのが当たり前だという感覚で育ち、「さす九」と言われかねない九州男児でした” 『つくられる子どもの性差』の森口佑介先生と中野円佳さんとの対談が記事に! OTEMOTO by ハリズリー o-temoto.com/akiko-kobayash…

「なぜ人間は、無自覚に偏ったジェンダー意識を持つようになるのか」 「こどもは親が期待することや教員が示したことを内面化し、それに沿った行動をしがち」 森口佑介さん 森口佑介『つくられる子どもの性差: 「女脳」「男脳」は存在しない』(光文社新書 ) と中野円佳さん中野円佳『教育にひそむジェンダー』 ともに子育て中のジェンダー研究者による考察です。 o-temoto.com/akiko-kobayash…