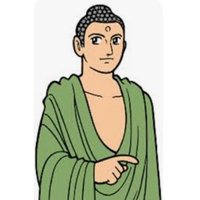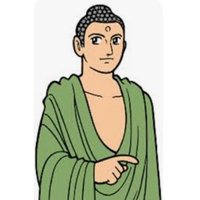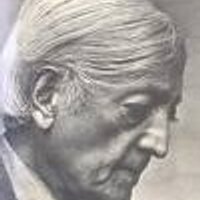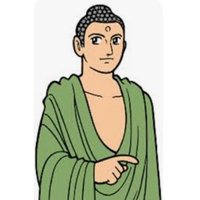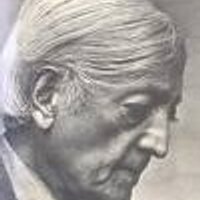sunふじ
@sunjurikell
ID: 843650106666569728
20-03-2017 02:27:14
14,14K Tweet
93 Followers
673 Following






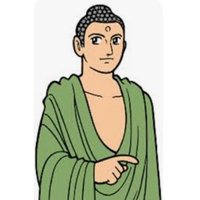

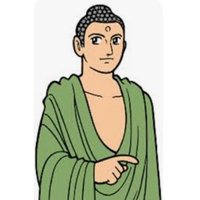



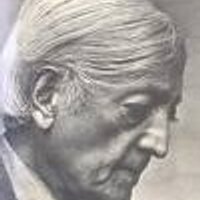

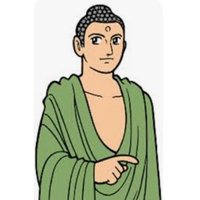




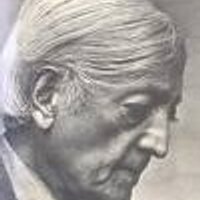

@sunjurikell
ID: 843650106666569728
20-03-2017 02:27:14
14,14K Tweet
93 Followers
673 Following